金融機関に融資を打診するタイミングを考えてみる!
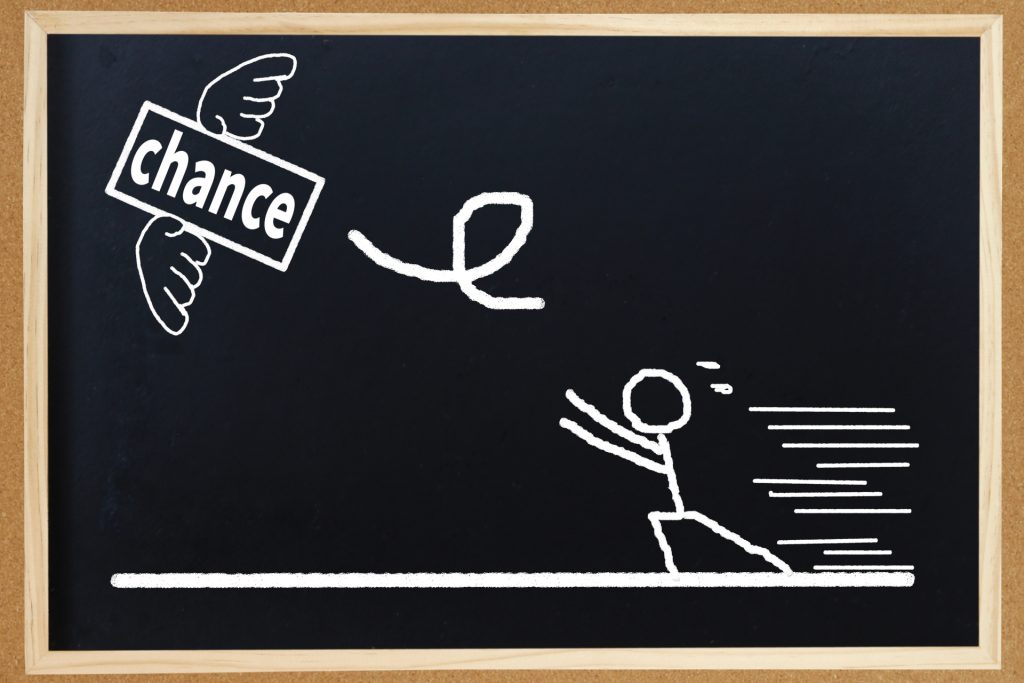
融資は企業運営にとって必要不可欠なものです。
しかしながら、
「融資はいつ申し込めば良いだろう?」
「決算書の内容が厳しいが、このタイミングだと融資を申し込んでも謝絶されるのではないだろうか?」
「融資を申込んで謝絶された場合、再度融資を申込むタイミングとして一般的に6ヶ月後と言われているが本当だろうか?」
経営者はいつも資金繰りは気にしているはずですので必要な融資額や時期は分かっていると思います。
それにも関わらず金融機関の担当者に融資を申込むタイミングというのは悩ましいことです。
ここでは、金融機関に融資を打診するタイミングについて考えてみますので、金融機関に融資を打診するタイミングに悩んでいる経営者は是非、参考にして下さい。
この記事に関する目次
1.決算書ができたタイミング
決算書ができたタイミングが金融機関に融資を打診するベストなタイミングになります。
金融機関の担当者は融資残高があれば必ず決算書の提出を求めてきます。
特に決算書が黒字であり、各種の財務指標が前期より改善されていれば融資申込のベストのタイミングともいえます。
何より、決算書だけで評価して貰えます。(融資申込のタイミングが遅いと追加で試算表等を求められ手間が掛かってしまいます。)
このにタイミングに今期必要な調達額を打診することで決算書をもとに融資の申込が可能となります。
ここで通常担当者から聞かれることは
① 今期の必要な調達額(=借入額)
② 調達予定時期
③ どこの金融機関から幾ら予定しているのか
になります。
この時、決算書とともに、簡単でも良いので事業計画を提出すると融資の可能性が非常に高まります。
この事業計画で記載すべき事項としては
① 損益計画(前期対比)
② 損益計画の根拠
特に、売上が伸び、経費については売上に合わせた経費の伸びや経費の削減や見直しが表記され前期に比べて利益が伸びていれば大丈夫です。
なぜ、簡単でも良いので事業計画があれば良いというのは、担当者が融資の稟議書を書き易く(上司に提出し易くするため)するためになります。
ちなみに、この事業計画には、担当者から聞かれるであろう、今期の調達額やどこの金融機関から幾ら借入を予定しているのかは記載する必要はありません。
あらかじめこれを記載してしまうと表記に縛られてしまう可能性があるため、調達額と調達金融機関に柔軟性を持たせることが必要とお考え下さい。
なお、決算書を提出し融資を打診したにもかかわらず、金融機関の対応が遅い場合は、この決算書から融資の対応が前向きでないためと判断した方が良いかもしれません。
※決算書の数値を資産査定(企業格付け)に反映させている期間は考慮が必要かもしれません
この場合、別な金融機関に融資を早めに打診しなければ今期に必要な資金を調達する対応が後手になり資金繰りが厳しくなることが予想されますので注意が必要です。
2.試算表で融資を申込むタイミング
(1)預金残高があり、単月黒字でかつ累積黒字であるタイミング
決算書が赤字であった場合や決算報告時に上手く融資の申込がいかなかった場合でも、試算表上、預金残高があり、単月黒字でかつ累積黒字であるタイミングが金融機関の担当者にとっては融資が取組易いタイミングとなります。
決算時に上手く融資が上手くいかなかった場合でも金融機関は融資を取組たいと考えています。
そのため、試算表上、預金残高があり、単月黒字でかつ累積黒字であるタイミングは金融機関にとれば「決算は赤字であったが業績が安定化してきている。また預金残高もあり資金繰りも改善方向にある」ことで稟議書が起案し易いタイミングとなり結果として融資が取組易いタイミングとなります。
(2) 預金残高は少ないが、単月黒字でかつ累積黒字であるタイミング
決算書が赤字であった場合や決算報告時に上手く融資の申込がいかなかった場合でも、試算表上、預金残高は少ないが、単月黒字でかつ累積黒字であるタイミングは金融機関の担当者にとっては融資に取組易いタイミングとなります。
これは金融機関にとれば、事業運営は上手く行っているが売上が上がっていることもあり、預金残高が少ないことで増加運転資金を取り組むチャンスになります。
なお、この場合、預金残高が少ないことで資金繰りが厳しいのではと思われる可能性もありますので、資金繰り表(融資を受けることで事業が上手くいき、預金残高も増加していき資金繰りの安定性も図れる)を提出することで融資の可能性が高まるとお考え下さい。
(3) 累積赤字だが単月黒字のタイミング
決算書が赤字であった場合や決算報告時に上手く融資の申込がいかなかった場合でも、例え累積赤字があっても黒字になったタイミングは金融機関の担当者にとっては融資に取組易いタイミングとなります。
これは金融機関にとれば、事業運営が上手くいきはじめたことを拠り所に融資稟議を書き易いタイミングとなります。
3.新しい融資制度が発表されたタイミング
新しい融資制度が発表されたタイミングは金融機関の担当者は新しい融資制度の説明に来るものです。
この時、担当者は他の金融機関がセールスに来る前(この融資商品を取り組まれる前)に対応したいと考えるものです。
担当者は他行に先駆け自行での融資申込をして欲しい(他行にこの融資チャンスを取られたくない)と考え、支店内でも積極セールスなどの号令がかかります。
また、制度自体ができたばかりの時は、日本政策金融公庫や信用保証協会、金融機関も制度が活用された実績が必要な為、制度ができた時には比較的審査が甘くなる傾向があり融資取上げにも積極的に対応してくれるケースが多いです。
4.2月・8月のタイミング
金融機関にとって決算(3月)・中間決算(9月)が締まるタイミングの前(2月・8月)は、支店にとって業績評価(長期借入金の純増額等)の追い込みを始めるタイミングになります。
特に、支店の業績のみならず担当者や支店長などの個人的な評価の締めも決算(3月)・中間決算(9月)のタイミングになります。
(支店長や役職者といわれる人はボーナス評価に直結します。業績評価で自身の査定に直結し人事昇格にも影響します。)
※近頃は、評価の締めは4半期毎(3ヶ月毎)という金融機関もあり一概には言えませんが。
その為、支店や個人の評価のためにも少々無理をしてでも融資を取り組もうと思うので、このタイミングも融資申込には良いタイミングだとお考え頂いて良いと思います。
なお、3月中旬や9月中旬に融資を打診しても積極的に動いてくれないかもしれません。
これは、融資に取り組んだとしても間に合わない(=3月末・9月末に融資実績に間に合う企業を優先しようと考える)ため、担当者は4月以降や10月以降で良いかなと考え後送りになる可能性があります。
また、4月以降や10月以降の場合、審査部も3月・9月の審査繁忙期に比べ比較的審査業務に余裕があるため、融資審査が期末よりも厳しくなることがあるためです。
5.既存金融機関から新規融資の打診があったタイミング
金融機関からの新規融資の打診があったタイミングは、決算書の内容の分析、支店内での調整が完了していることが前提になっての打診となります。
金融機関からの打診に対して積極的に対応することをお勧めしますが、これが信用保証協会付き融資であれば他行(メイン行)でも調達可能ですので、あくまでプロパー融資での打診が検討するうえでの前提になります。
なお、保証協会付き融資での新規融資の打診(既に信用保証協会に保証枠の確認をしている場合)に対して安易に受けてしまうと、今後融資を申込む時にメイン行との調整(例えば、信用保証協会付き融資とプロパー融資との併用申込の場合、信用保証協会の枠がないといった問題が生じる可能性があります。)や今後の真水を含めた借換などの調整(借換しようにも既に信用保証協会の枠がいっぱいな状況で真水の部分がない等)が厳しくなる可能性があるので注意が必要です。
6.取引のない金融機関から新規融資の打診があったタイミング
取引のない金融機関から新規融資の打診があったタイミングは、積極的に対応することをお勧めします。
この場合、取引のない金融機関はあらかじめ帝国データバンクや商工リサーチの評点などから融資の取り組みを検討できる企業として新規融資の打診があったものと考えて間違いないです。
そのため、対応時に求められる書類(履歴事項全部証明書、過去3期分の決算書や借入の分かる書類)は提出して頂いて積極的に対応することが良いでしょう。
なお、取引のない金融機関からの新規融資の打診は基本的にプロパー融資が前提になるため、この打診が信用保証協会付き融資であれば既存行で調達可能ですので、あくまでプロパー融資での検討が前提になりますのでご注意下さい。
7.設備投資が発生するタイミング
金融機関にとって設備資金は見積書があるので資金使途が明確です。
また、設備資金の融資を行う金融機関としても見積書の取引先(設備購入先業者)へ融資金を振り込むことになるので融資に取組易いです。
確かに、設備資金の借入も負債ですので決算書や試算表上、運転資金して借り入れた長期借入金と同様に表示されるため、借入過多に見え、将来的に運転資金の調達が厳しくなるのではないかとお考えの経営者もいると思います。
しかしながら、設備資金を借入する際に、運転資金が必要になることを事前に金融機関の担当者に打診しておくことで運転資金に対しても積極的に対応して貰えることが多いです。
また、設備資金を自己資金でまかなったために、将来的に運転資金が厳しくなることが予想されているのであれば資金繰り上本末転倒になります。
なお、注意すべき事項は、設備資金は運転資金には転用はできません。
設備資金は固定資産の明細などに表示されますので運転資金への転用すると後々資金使途違反として借入自体が難しくなります。
もちろん設備投資完了後に設備資金の融資申込をしても金融機関としては設備資金の借入申込としての融資取組は厳しいとお考え下さい。
8.補助金が採択されたタイミング
金融機関にとって助成金や補助金の採択(交付決定)があり、この結果もとに融資を行うことは資金使途が明確です。
また、補助金の採択(交付決定)を担保に融資を行う金融機関は、採択(交付決定)の補助金額まで融資が取組易いです。
なお、補助金の申請書には借入予定行と借入予定金額の記載する欄がありますので、申請前に借入を予定している金融機関に打診しておくことでスムーズに融資が出やすくなります。
確かに、補助金の採択(交付決定)をもととした借入は短期借入金として計上されますが借入過多とみられてしまい将来的に運転資金の調達が厳しくなるのではないかとお考えの経営者の方も多いのではないでしょうか。
しかしながら、助成金の採択(交付決定)を担保に借入する際に、今後、運転資金が必要になることを事前に金融機関の担当者に打診しておくことで運転資金に対しても積極的に対応して貰えることが多いです。
また、補助金の対象事業を自己資金でまかなったために、将来的に運転資金が厳しくなることが予想されているのであれば本末転倒になります。
注意すべき事項は、補助金の交付決定額が融資限度額になり、補助金が入る口座は借入行への指定を融資条件されることになります。
あわせて、補助金の交付決定をもとに信用保証協会付き融資を調達した場合、概算払いがされた場合融資内入れは前提となります。
また、補助金相当額を融資として取り組んだことで信用保証協会の与信枠がいっぱいとなり、短期借入金を返済しないと新規で信用保証協会付き融資を調達できない可能性もありますので注意が必要です。
9.まとめ
金融機関に融資を打診するタイミングは思っていたより多かったではないでしょうか?
また、決算が赤字企業や試算表(月次・累積に関わらず)が赤字企業も多いと思います。
この場合、金融機関に融資を打診するタイミングは、早めに取引金融機関に対し融資を打診するようにすることが良いと考えています。
なお、決算書や試算表を提出し融資を打診したにもかかわらず、金融機関の対応が遅い場合は、現状の決算書や試算表からは融資について前向きでないと判断した方が良いかもしれません。
特に、決算書や試算表が赤字であればなおさらです。
金融機関の担当者としては赤字企業には融資が厳しいと考えるのが普通です。
資金繰り上必ず融資が必要であれば、取引金融機関に対し融資を早めに打診しなければ必要な資金を調達する対応が後手になり資金繰りが厳しくなることが予想されますのでくれぐれも注意して下さい。
資金繰りが厳しく、資金調達の準備が必要、自社に合った融資制度を知りたい、
手続きが難しそうで進める自信がないなど
元銀行員が融資獲得まで
サポートします!
- 資金繰りが厳しく、資金調達の準備をしなければ心配。
- 自分に合った融資制度を知りたい。
- 手続きはが難しそうで、自分ではなかなか進められない。
元銀行員が融資獲得まで
サポートします!
- 資金繰りが厳しく、資金調達の準備をしなければ心配。
- 自分に合った融資制度を知りたい。
- 手続きはが難しそうで、自分ではなかなか進められない。
